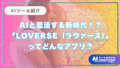2025年8月22日「富岳NEXTが日米連携でAI性能100倍に!」というニュースが飛び込んできました!AI界隈のビッグニュースをざっくり噛み砕いて紹介します。スーパーコンピュータって聞くと一見して難しそうなので、今回はできるだけカジュアルにまとめてみました。これを読めば、「富岳NEXTってすごそう!」というワクワク感が伝わるはず!
そもそも「富岳」って?
「富岳(ふがく)」は、理化学研究所(RIKEN)と富士通が開発した日本のスーパーコンピュータ。2020年には世界ランキングで1位を獲得したこともある超高性能マシンです。気象予測や創薬シミュレーション、さらにはコロナ禍での飛沫シミュレーションでも大活躍しました。
富岳NEXTとは?
「富岳NEXT」はその後継機で、2030年ごろの稼働を目指して開発中。今回の大きなポイントは、なんといってもアプリケーション性能を最大で100倍にする! という目標です。
「アプリケーション性能」とは、単にマシンがどれくらい速いかではなく、実際に研究やAI学習などの「実際の使い方」でどのくらい成果を出せるか、という指標のこと。ここを100倍にするのはめちゃくちゃ大きなインパクトです。
日米連携のポイント
- RIKEN(日本)が中心
- 富士通(日本)が次世代CPU「MONAKA-X(仮称)」を開発
- NVIDIA(アメリカ)がGPUを提供
つまり、日本の技術とアメリカの最新GPU技術をがっちり組み合わせるプロジェクトなんです。これまでの富岳はCPUだけで勝負してたので、GPU導入は大きな変化です!
「GPU」ってなに?
GPUとは「Graphics Processing Unit」の略。もともとはゲームや映像処理用のチップなんですが、AIや科学計算を超並列で処理するのが得意で、今やAIの学習には欠かせない存在になっています。
どうやって100倍に?
- ハードウェア性能:およそ 5倍
- ソフト・アルゴリズムの工夫:さらに 10〜20倍
これらを合わせて「最大100倍」を目指すとのこと。単純にハードを強化するだけじゃなく、ソフト側の工夫が大事っていうのがポイントなんです!
「ゼタスケール」って何?
「ゼタスケール」とは、1秒間に10の21乗回の計算ができるレベルの性能を指します。ざっくり言うと「とんでもなく速いコンピュータ」のこと。
富岳NEXTは、このゼタスケールを世界で初めてAI向けに実現しようとしているんです。
省エネ性能もすごい
「40メガワット」という消費電力で設計されています。これは富岳と同じくらいの電力なんですが、その中で100倍の性能を出そうとしているんです。効率の進化がすごすぎる…!
「AI for Science」って?
これは「科学のためのAI」というコンセプトで、
- 仮説をAIが自動で立てて検証
- 実験やシミュレーションを自動化
- コードもAIが自動生成
みたいに、研究のサイクルをAIで加速させようという試みです。研究者の働き方自体が変わるかもしれません。
まとめ
富岳NEXTは、
- 日米連携(RIKEN・富士通・NVIDIA)
- アプリ性能100倍!
- ゼタスケールAIプラットフォーム
- 省エネで効率的
という要素を兼ね備えた次世代スーパーコンピュータ。これは「科学研究のやり方」を根本から変える可能性があるプロジェクトです。AIとHPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)の融合が、新しい時代を作るかもしれません。2030年が待ち遠しいですね!