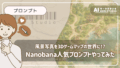昨今SNSやテレビ等でよく耳にする「デジタル終活」。
「終活ってエンディングノート書いたり、お墓のこと考えたりするやつでしょ?」
と思っている方も多いはず。実はその“デジタル版”が今、注目されているんです。
今回はそんな「デジタル終活」とそのサポートを担ってくれるAIについて、紹介していきたいと思います。
デジタル終活とは?
簡単に言うと、ネットやスマホに関わる財産やデータを整理しておくこと。
たとえば…
- ネット銀行や証券口座、仮想通貨
- SNSやメール、サブスク契約
- クラウドに保存してある写真や動画
これらを「残したいもの」「消したいもの」「家族に引き継ぎたいもの」に仕分けしておくのがデジタル終活です。
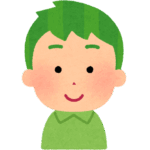
もし整理せずに突然いなくなったら…
「銀行口座が見つからない!」「SNSに知らない写真が残りっぱなし…」なんてことも起こり得るかも。それを探したり整理するのは家族にとってはかなり大変。
だからこそ、事前に整えておくことが大事なんですね。
AIを使うメリットは?
なぜわざわざ AI を入れるのか。それは、終活にはいくつもの「手間」「迷い」「抜け」が潜んでいるからです。
- 整理の面倒を減らす
山ほどあるアカウント、写真、契約。AI による自動分類で、「これは銀行」「これは SNS」「これは思い出」のようにラベル付けできると助かります。 - 忘れていたものを発見できるかも
長い間使っていなかったアカウント、古いクラウドサービス。AI は過去データを分析して、思い出せなかったものをリストに出してくれる可能性があります。 - 意思表現を支援してくれる
「残したい言葉」「伝えたいこと」を文章化するのは意外と難しいもの。AI に質問をされながら思いを整理できる形式だと、気持ちがまとまりやすくなります。 - 家族の負担を軽くする
故人アカウントの手続き、データ整理などを家族がやるのは精神的にも時間的にも大きなコスト。AI が手順のガイドをしてくれたり、自動処理の候補を示してくれると時間はもちろん、気持ちも楽です。 - 思い出を「残す」表現の多様化
故人の声・表情・言葉を使って、家族と “会話できるような体験” を提供するサービスも出てきています。
こうしたメリットを活かせれば、より「本人らしい終活」ができ、家族もスムーズにそれを受け取れるわけです。
注目の AI サービス例
ここではAIを活用したデジタル終活のサービスを紹介します。
故人の音声や言葉を再現し、AI デジタルヒューマンとして“会話体験”を実現するサービスです。表情やリップシンクもリアルに再現され、まるでその人がそこにいるかのような追悼体験が可能になります。
遺された家族が「また話したい」と思う瞬間に、慰めになるかもしれませんね。ただし、倫理的配慮や残された遺族の気持ちを重視する必要があります。

(画面はTalkMemorial.ai様の公式サイトをキャプチャーしています)
終活相談AI(株式会社ファミトラ)(リンク先に公式LINEのQRコードがあります)
ChatGPTの技術をベースにした「終活相談AI」です。このチャットボットは、資産整理や相続、老後の介護、健康管理など終活に関する質問に対応しておりLINEで友だち追加するだけで、専門的なアドバイスを無料で受けることができます。
家族が亡くなった時、遺族はその対応に忙しなく追われます。そんな時、何時でも手軽に相談出来るのは心強いですね。

(画面は株式会社ファミトラ様の公式サイトをキャプチャーしています)
特定の「終活サービス」ではありませんが、柔軟に使えるのが大きな魅力。
- リストアップ支援
「持っているアカウントを書き出してみましょう」と促しながら整理をサポート。 - 質問形式で思いを引き出す
「このSNSは残したいですか?」「この写真は誰に見てほしいですか?」と会話を通じて希望をまとめられる。 - 文章化・言語化
家族に残す手紙やデジタルエンディングノートを自然な文章に整えてくれる。 - 専門用語を噛み砕く
相続やプライバシーの法律的な説明をわかりやすい言葉に変換。
日常的に使えるため、「まず ChatGPT に相談してみる」ことからデジタル終活を始めても良いでしょう。
AI を使うときの注意点/リスク
AI の活用は魅力的な反面、いくつか気をつけたい点もあります。
- 最終判断を AI に丸投げしない
AI は補助役。特に法律・相続・税金に関わる内容は、専門家のチェックが不可欠です。文章作成支援や要約支援は得意でも、法律的な妥当性まで保証するわけではありません。 - プライバシー・セキュリティ
故人データ、パスワードや金融情報といったセンシティブ情報を AI に扱わせるので、暗号化・アクセス制御・個人情報保護の観点は厳しくチェックすべきです。 - 遺族感情とのバランス
AI による “故人との会話体験” が癒しになる人もいれば、違和感を抱く人もいます。家族の気持ちを尊重しながら導入を検討することが大切です。
はじめて AI を使ったデジタル終活を始める方法(ステップ)
- 身の回りのデジタル資産をリスト化
SNS、クラウド、メール、契約サービス、写真・動画など、思いつく限り書き出す。 - AI 補助ツールで整理を試してみる
思い出写真を整理するアプリや、遺言支援チャットを使ってみる。 - 希望を“質問形式”で書き残す
AI に「どの SNS は残したい?どのデータは削除したい?」と質問できるような形式にしておく。 - 信頼できる人にアクセス方法を伝える
パスワードや解錠キー、AI へのアクセス情報などを信頼できる人や家族に預けておく。 - 必要な場合は専門家に最終チェックを
作成した内容に資産等が含まれている場合はトラブルを回避する為に弁護士・行政書士・税理士などに確認してもらう。
おわりに
デジタル終活は、「見えない遺産」を整理し、未来につなぐ大切なプロセスです。AI はその助け手になり得ますが、「すべて任せる魔法の箱」ではありません。本人の思い、家族の気持ち、技術と倫理のバランスを見ながら、少しずつ取り入れていくのが現実的です。
合わせて読みたい
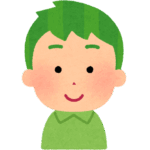
ここまで記事を読んで頂きありがとうございます!デジタル時代の今だからこそ、誰しもが直面する問題かもしれませんね。
さて、今回の記事で紹介したChatGPTは過去記事でも特集しております。AIを知りたい方、ChatGPTについてもっと詳しく!という方は是非、ご一読ください!